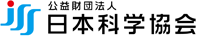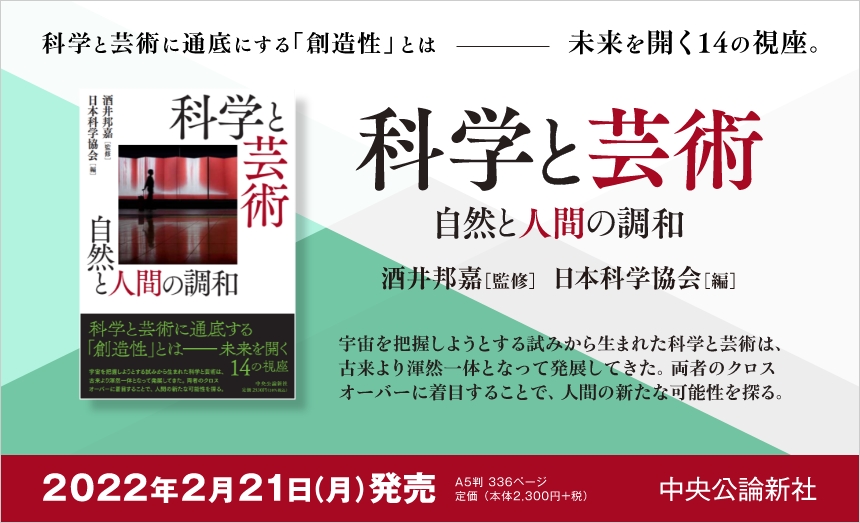
各章の概要
はじめに
酒井 邦嘉(科学隣接領域研究会リーダー)
第I部 創造と想像
-
第1章(対談)芸術と科学の邂逅
-


千住 博(日本画家)
✕
酒井 邦嘉(東京大学大学院総合文化研究科教授)
-
第2章ベートーヴェンはなぜすごいのか
曽我 大介
(東京ニューシティ管弦楽団正指揮者/作曲家) -
 クラシック音楽作曲家の代名詞、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。遺した名曲の数々は今なお私たちの心を打つ。ベートーヴェンのすごさは作品だけでなく、音楽と音楽家の社会的立場の価値観をも変えたこと。天才の「スゴさ」を幼少からの教育、創作の手法と思想から考察する。また巨匠が生涯悩まされた、持病の謎解きには近年、科学のメスがはいった。
クラシック音楽作曲家の代名詞、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。遺した名曲の数々は今なお私たちの心を打つ。ベートーヴェンのすごさは作品だけでなく、音楽と音楽家の社会的立場の価値観をも変えたこと。天才の「スゴさ」を幼少からの教育、創作の手法と思想から考察する。また巨匠が生涯悩まされた、持病の謎解きには近年、科学のメスがはいった。
-
第3章マンダラ:視覚化された最高真理
―そして芸術への傾斜―
正木 晃
(宗教学者) -
 人間相互の情報伝達は、おおむね言葉がになう。では、宗教が想定してきた最高真理は言葉で伝達できるか。世界中の宗教のほとんどは可能とみなしてきた。しかし、仏教だけは不可能とみなしてきた。なぜなら、開祖のゴータマ・ブッダが、仏教の最高真理にあたる「悟り」は、言葉では表現できず、ましてや伝達など不可能と主張したからだ。以来、仏教の歴史は、「悟り」とは何か、をめぐる試行錯誤の連続となった。この難問を、最後発の仏教である密教は、「悟り」を視覚化することで解決しようと試みた。それがマンダラである。本論考では、マンダラ開発の経緯、本来の機能などをまず説明し、日本伝来されると次第に芸術へと傾斜していった過程を、日本人の真理観や自然観と照らし合わせながら考察する。
人間相互の情報伝達は、おおむね言葉がになう。では、宗教が想定してきた最高真理は言葉で伝達できるか。世界中の宗教のほとんどは可能とみなしてきた。しかし、仏教だけは不可能とみなしてきた。なぜなら、開祖のゴータマ・ブッダが、仏教の最高真理にあたる「悟り」は、言葉では表現できず、ましてや伝達など不可能と主張したからだ。以来、仏教の歴史は、「悟り」とは何か、をめぐる試行錯誤の連続となった。この難問を、最後発の仏教である密教は、「悟り」を視覚化することで解決しようと試みた。それがマンダラである。本論考では、マンダラ開発の経緯、本来の機能などをまず説明し、日本伝来されると次第に芸術へと傾斜していった過程を、日本人の真理観や自然観と照らし合わせながら考察する。
-
第4章理学・工学・アート・デザインとウェルビーイング
前野 隆司
(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授) -
 理学、工学、アート、デザインの関係について学術的な知見を述べる。すなわち、理学とアートは基礎的な分野であるのに対し、工学とデザインは実用的な分野であることや、アートとデザインは感性に、理学と工学は理性に関連するという基本的分類について述べる。また、これらとウェルビーイングの関係についても述べる。すなわち、美しいものを創造する人は幸せであることや、ウェルビーイングは現在では科学の研究対象であることなどについて述べる。
理学、工学、アート、デザインの関係について学術的な知見を述べる。すなわち、理学とアートは基礎的な分野であるのに対し、工学とデザインは実用的な分野であることや、アートとデザインは感性に、理学と工学は理性に関連するという基本的分類について述べる。また、これらとウェルビーイングの関係についても述べる。すなわち、美しいものを創造する人は幸せであることや、ウェルビーイングは現在では科学の研究対象であることなどについて述べる。
第II部 人と生物
-
第5章「温故知新」の普遍性~能と論語とbeyond AI~
安田 登
(能楽師) -
 死者という異界の人(シテ)の魂を慰め、そして生者(ワキ・観客)自身もその生を生きなおす芸能が能楽である。「古」によって「新」が更新される。世阿弥は「古きを学び、新しきを賞する」と言った。それは論語の「温故而知新」が元となる。「知」とはおそらく孔子によって生み出された精神活動だ。そして、人類の到達した「知」の最先端がAIであろう。「古」から「新」へ至るための方法やAIの次の可能性を能と論語から読む。
死者という異界の人(シテ)の魂を慰め、そして生者(ワキ・観客)自身もその生を生きなおす芸能が能楽である。「古」によって「新」が更新される。世阿弥は「古きを学び、新しきを賞する」と言った。それは論語の「温故而知新」が元となる。「知」とはおそらく孔子によって生み出された精神活動だ。そして、人類の到達した「知」の最先端がAIであろう。「古」から「新」へ至るための方法やAIの次の可能性を能と論語から読む。
-
第6章歩行について:境界例からのライヴ・アート(生の芸術)考
外山 紀久子
(埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授) -
 「歩く」という動作は、ふだん意識されないありふれた身体運用に過ぎない。他方、パフォーマンス系のアートでは、歩行をめぐって多様なアプローチがなされてきた。私たちは歩くこと(二足直立歩行)で「人間」となり、文化を獲得し、大地・自然・世界から離脱するが、歩くことを通して文化と自然、人間と非人間の境界を横断するための技法もまた開発してきたのではないか。この問題を現代アートや舞踊のかなりマイナーな事例を通して考えていく。
「歩く」という動作は、ふだん意識されないありふれた身体運用に過ぎない。他方、パフォーマンス系のアートでは、歩行をめぐって多様なアプローチがなされてきた。私たちは歩くこと(二足直立歩行)で「人間」となり、文化を獲得し、大地・自然・世界から離脱するが、歩くことを通して文化と自然、人間と非人間の境界を横断するための技法もまた開発してきたのではないか。この問題を現代アートや舞踊のかなりマイナーな事例を通して考えていく。
-
第7章科学論の中の美と芸術ー近代日本の見た「実在」
岡本 拓司
(東京大学大学院総合文化研究科教授) -
 明治維新以降、科学が日本に大規模に導入されるのに伴い、種々の科学論も発表されるようになった。これらのうちには、美や芸術についての主張を展開するものもあり、その系統は、北輝次郎や篠原雄などの、進化論を議論の基礎に置くものと、田辺元や石原純の、同時代のドイツ哲学の学問分類や実在観を採用するものの二つに分けることができる。敗戦後にこれらはいったん消滅し、別系統でありながらやはり特定の実在観を前提とするマルクス主義科学論が主流となり、大学紛争後はパラダイム論がこれにとってかわることとなったが、その過程で美や芸術に関する議論は科学論では取り上げられなくなっていった。
明治維新以降、科学が日本に大規模に導入されるのに伴い、種々の科学論も発表されるようになった。これらのうちには、美や芸術についての主張を展開するものもあり、その系統は、北輝次郎や篠原雄などの、進化論を議論の基礎に置くものと、田辺元や石原純の、同時代のドイツ哲学の学問分類や実在観を採用するものの二つに分けることができる。敗戦後にこれらはいったん消滅し、別系統でありながらやはり特定の実在観を前提とするマルクス主義科学論が主流となり、大学紛争後はパラダイム論がこれにとってかわることとなったが、その過程で美や芸術に関する議論は科学論では取り上げられなくなっていった。
-
第8章科学と芸術をめぐる近代のパラドックス──ゲーテ自然科学における形態学と菌類生物の<ポリネーション>
前田 富士男
(慶應義塾大学名誉教授) -
 近代の自然世界は、神のような超越的な存在も神話的物語も許容しない。科学は合理的理論モデルを構築し、芸術は制作者の感性と想像力にもとづくイメージ世界を創出する。しかし、こうした取り組みは、今もなお豊かな生命的自然界にくらす人間に重いパラドックスを突きつける。本章は、芸術家で科学者だったゲーテによる植物・動物と第三の生物「菌類」の形態学研究をテーマに、パラドックスのありかとその豊かさの発見法を試論として提示する。
近代の自然世界は、神のような超越的な存在も神話的物語も許容しない。科学は合理的理論モデルを構築し、芸術は制作者の感性と想像力にもとづくイメージ世界を創出する。しかし、こうした取り組みは、今もなお豊かな生命的自然界にくらす人間に重いパラドックスを突きつける。本章は、芸術家で科学者だったゲーテによる植物・動物と第三の生物「菌類」の形態学研究をテーマに、パラドックスのありかとその豊かさの発見法を試論として提示する。
-
第9章生命を主体とする哲学―南方熊楠とユクスキュル
松居 竜五
(龍谷大学国際学部国際文化学科教授) -
 南方熊楠(みなかた・くまぐす、一八六七~一九四一)とユクスキュル(Jakob Johann von Uexküll一八六四~一九四四)は、ともに十九世紀末から二十世紀にかけて、生命を主体とする哲学を打ち立てた。「南方マンダラ」として知られる熊楠の思想は、人間にも他の生物にも適用できる世界像を示している。これは、ユクスキュルが生物はすべて独自の「環世界」を生きており、人間もそうした存在の一つに過ぎないと語ったことと軌を一にしていると考えられる。
南方熊楠(みなかた・くまぐす、一八六七~一九四一)とユクスキュル(Jakob Johann von Uexküll一八六四~一九四四)は、ともに十九世紀末から二十世紀にかけて、生命を主体とする哲学を打ち立てた。「南方マンダラ」として知られる熊楠の思想は、人間にも他の生物にも適用できる世界像を示している。これは、ユクスキュルが生物はすべて独自の「環世界」を生きており、人間もそうした存在の一つに過ぎないと語ったことと軌を一にしていると考えられる。
-
第10章四次元の芸術――南方熊楠と鈴木大拙からはじまる
安藤 礼二
(多摩美術大学 図書館長/同大学美術学部 教授) -
 南方熊楠と鈴木大拙は、文字通り世界が一つになった近代という時代に、この極東の列島に育まれた独自の宗教、「東方大乗仏教」のもつ可能性をあらためて考え抜いた。その際、二人とも生物学と心理学に代表される科学的な思考方法を無視することはなかった。むしろ積極的に学びとり、西洋の科学と東洋の宗教が一つに交わる地点に、森羅万象あらゆるものを発生させる「心」を据えた。それは同時代の芸術家たちの営為と深く共振するものであった。
南方熊楠と鈴木大拙は、文字通り世界が一つになった近代という時代に、この極東の列島に育まれた独自の宗教、「東方大乗仏教」のもつ可能性をあらためて考え抜いた。その際、二人とも生物学と心理学に代表される科学的な思考方法を無視することはなかった。むしろ積極的に学びとり、西洋の科学と東洋の宗教が一つに交わる地点に、森羅万象あらゆるものを発生させる「心」を据えた。それは同時代の芸術家たちの営為と深く共振するものであった。
第III部 都市と自然
-
第11章都市・まち・建築の熱環境の可視化
梅干野 晁
(東京工業大学名誉教授/放送大学客員教授) -
 都市・まち・建築、私たちの生活空間であるが、そこの熱環境は目にみえないのでなじみが薄い。これをカラーコードの熱画像により、三次元空間の時間変化も含めて可視化することで感性に訴えたい。従来の数式やグラフに加えてより熱環境が理解できるのではなかろうか。その上で、まちづくりの具体的なあり方を考えてみたい。全球赤外線放射カメラで収録した全球熱画像で、私たちを取り囲むすべての表面温度の実態を可視化する。さらに、過去や未来の熱環境について3D‐CADと熱収支シミュレーションで表面温度を求め、それを可視化する。
都市・まち・建築、私たちの生活空間であるが、そこの熱環境は目にみえないのでなじみが薄い。これをカラーコードの熱画像により、三次元空間の時間変化も含めて可視化することで感性に訴えたい。従来の数式やグラフに加えてより熱環境が理解できるのではなかろうか。その上で、まちづくりの具体的なあり方を考えてみたい。全球赤外線放射カメラで収録した全球熱画像で、私たちを取り囲むすべての表面温度の実態を可視化する。さらに、過去や未来の熱環境について3D‐CADと熱収支シミュレーションで表面温度を求め、それを可視化する。
-
第12章科学と芸術をつなぐ多孔性モデル ──生態学的都市論から見た世界
田中 純
(東京大学大学院総合文化研究科教授) -
 本章では、とくに建築・都市空間における「多孔性」の概念を主軸として、科学と芸術に共通する空間モデルを考察する。いち早く多孔性の概念を導入したヴァルター・ベンヤミンの都市論を佐々木正人らの生態心理学的な環境存在論と結びつけることで「生態学的都市論」の観点を提案し、ベンヤミンと同時代の多孔的建築物から現代の哲学・建築理論にいたるさまざまな実例を通して、科学と芸術をつなぐ多孔性モデルの理論的な可能性を提示する。
本章では、とくに建築・都市空間における「多孔性」の概念を主軸として、科学と芸術に共通する空間モデルを考察する。いち早く多孔性の概念を導入したヴァルター・ベンヤミンの都市論を佐々木正人らの生態心理学的な環境存在論と結びつけることで「生態学的都市論」の観点を提案し、ベンヤミンと同時代の多孔的建築物から現代の哲学・建築理論にいたるさまざまな実例を通して、科学と芸術をつなぐ多孔性モデルの理論的な可能性を提示する。
-
第13章庭園芸術が問う技術時代の総合芸術
後藤 文子
(慶應義塾大学文学部人文社会学科教授) -
 様式問題を一つの重要な基礎とする一九世紀以来の美術史研究の伝統において、長らく庭園芸術は、人間の手になる造形物としての建築に付随するものと位置づけられてきた。しかし芸術の規範である様式そのものがもはや成立しなくなった近・現代にあって、庭園芸術それ自体が、実は、新しい庭園の創出を模索する営みを通して、芸術にとってそれがもつ本質的な意義を問いかけていた。本稿ではこの問題を近代のデザイン問題として検討する。
様式問題を一つの重要な基礎とする一九世紀以来の美術史研究の伝統において、長らく庭園芸術は、人間の手になる造形物としての建築に付随するものと位置づけられてきた。しかし芸術の規範である様式そのものがもはや成立しなくなった近・現代にあって、庭園芸術それ自体が、実は、新しい庭園の創出を模索する営みを通して、芸術にとってそれがもつ本質的な意義を問いかけていた。本稿ではこの問題を近代のデザイン問題として検討する。
-
第14章人間と自然の関係の文化「庭」の今
岡田 憲久
(名古屋造形大学特任教授・景観設計室タブラ・ラサ主宰) -
 今日、都市はあまりにも人工的に改変され、それぞれの場での自然の気脈が見えない。たった一つの小さな場であっても、マクロな自然との連動性が持たれていなければ、その空間は生きた空間としての力を持たない。人間は自然そのものではない。人間存在は、生命の一員である存在であることと、生命からあまりにもかけ離れてしまった存在であることの二面性を持つ。この二面性の境界の人間の在り方の姿を、人間と自然の関係の文化「にわ」から問う。
今日、都市はあまりにも人工的に改変され、それぞれの場での自然の気脈が見えない。たった一つの小さな場であっても、マクロな自然との連動性が持たれていなければ、その空間は生きた空間としての力を持たない。人間は自然そのものではない。人間存在は、生命の一員である存在であることと、生命からあまりにもかけ離れてしまった存在であることの二面性を持つ。この二面性の境界の人間の在り方の姿を、人間と自然の関係の文化「にわ」から問う。